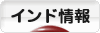今年の冬は、例年に比べ少々冷え込む気がする。とはいえ、日中は強い陽光が降り注ぎ、十分に暖かいバンガロール。クリスマスムードは「強制的に」演出せねば、年の瀬感が出てこない。
というわけで、クリスマスツリーを飾り付け、庭には紅白のポインセチアを配すなど、雰囲気を盛り上げている。
先ほど、夕暮れの庭を歩きながら思い至った。インドに暮らし始めて5度目の年の瀬。今年ほど、ゆったりとした心持ちで迎えられたことはないということを。
思えば常に、ドタバタとした日々であった。世間には大っぴらに公表できぬ「大小の家庭内波乱」も含め、なかなか心穏やかになれない日々が続いていた。
去年などは、だからこそ、「アーユルヴェーダ道場」に1週間籠って、心身のデトックスを図ったのだった。あれはよかった。今年もまた行きたいくらいだ。夫は嫌がるかもしれんが、行くかもしれん。
過去に比して、日本から帰国して以来のここ数週間(短っ!)、実に平和である。平和すぎて、年末の休暇の予定を立てることも忘れてをり。
ま、なるようになるであろう。
■チャリティ・ティーパーティ。家族平和があってこその充実駐在生活
気がつけば、10回を超えたチャリティ・ティーパーティ。講座はしかし、まだ3種類を複数回行うばかり。というのも、次々に新しい人たちが赴任して来る状況にあって、過去の講座が人気なのである。
特に今回行った『アーユルヴェーダ&インド自然派コスメティクス』は、聞く人たちの真剣度が違う。具体的なコスメティクスの使用感を試してもらいつつ、互いの情報交換も加わり、なかなかに充実の内容なのだ。
もちろん、資料の濃度も高いと自負している。
基本は、「せっかく縁あってインドに来たのだから、住んでいる間くらいは楽しくやろうではないか」というコンセプトのもと、である。
概ね、日本の企業人というのは、「妻子はさておいて、仕事」の意識が強いように思う。いや、心の中では違っていても、表向きには「仕事優先」な社会であったろう。
しかし、異国の地では、そうはいかない。妻子がそれなりに平穏に暮らしていなければ、仕事どころではない。これは米国在住時から感じていたことだ。
家庭の事情がビジネスに影響を与えるという場面を、少なからず目にして来た。
海外赴任をするからには、「嫌がる家族をたしなめつつ」ではなく、「家族の前向きな協力を得て」の方が、どれだけ仕事にも好影響を与えるか知れない。
とわたしは切に思っているのだが、世間はそうは思っていないのかもしれない。
が、ともあれ、ジャパニーズビジネスマンが異国の地でも力を発揮し、日本の経済に貢献するには、その妻たちの平和な異国での暮らしがあってこそ。なのである。多分。
というわけで、インドの地域社会への貢献を行うと同時に、日本の奥様方へ有益な情報を提供する。地道ながらも楽しみつつ、方向性を模索しつつ、続けて行く所存である。
来年は、新しい講座を数本用意する予定。手始めは、インド生活を前にして、インドの概要を「勉強」すべく講座を考えている。
これは、駐在員夫人よりはむしろ、駐在員にも興味を持って欲しい講座である。その機会を将来得る可能性も高いので、念入りに資料を作成することになりそうだ。
夫アルヴィンドと出会って、来年で15年。彼と出会って得たことは数えきれないし、わが人生は、大いなる方向転換を遂げた。今、インドに住んでいるという事実からして、彼と出会ったからこそ、である。
加えて、彼のバックグラウンド(学歴/キャリア)を通して、わたしだけの力では決して出会うことはなかったであろう人々との交流を持てることが、興味深く、ありがたい。
わたしが30歳にしてニューヨークへ渡り、英語の勉強をし直そうと思ったきっかけは、「海外取材をするときに通訳なしで行いたい」という目的があったからだ。
しかしそれ以上の出会いや収穫があったということは、敢えて例を挙げるまでもないだろう。
まだまだ未熟で不完全であるとはいえ、そこそこに英語を操れることが、わたしの人生の「視界を広げる」ことに、どれほど役に立っているかしれない。
無論、英語が話せればそれでいい、という話でもないのだが。
米国では、結婚前のカップルでも、パートナーをビジネスのパーティなどに同伴することは一般的である。従っては、彼の社交に同伴して久しい。
企業のパーティやイヴェントをはじめ、彼が卒業した大学(MIT: マサチューセッツ工科大学)やMBA(Wharton)などのアラムナイやリユニオン(同窓会)出席したことも多々ある。
米国を離れても、ムンバイで、バンガロールで、大小のアラムナイをはじめとする集まりに参加して来た。
特に2006年にムンバイで開かれたWhartonのアラムナイは、インド移住直後だったわたしにとって、格好のムンバイツアーともなり、夫もさることながら、わたしが思い切り楽しんだ。
以下はそのときの記録である。
●同窓会。伴侶のためのツアーに参加
●闇夜を彩る花火の下で
●You are a future!
前置きが長くなったが、バンガロールにはWhartonの卒業生も少なくなく、小さな会合も年に数回開かれて来た。
参加者の多くは、起業家、トップエグゼクティヴなど、インドのビジネス界において少なからず存在感のある人が多数だ。たいていが「夫婦揃って名門校出自」な場合が多い会合にあって、わたしはかなり、浮いている。
「あなたも、アルヴィンドと同じ学校?」
といつも聞かれる。
「日本人すら知っている人が少ない、地方都市の大学出身なんですよ〜。ワハハ」
と、笑ってお茶を濁しつつ、自分の仕事などについて語る。名門校の出自じゃなくとも、見下したり、話をやめて立ち去る人などはいない。従っては、わたしも一緒に楽しむことができる。
その後、仕事で取材をさせてもらった人も少なくない。
さて、先週の水曜日は、Whartonだけでなく、ハーバードやスタンフォード、シカゴ、MITなど、米国の名門MBAの同窓生が集まるカジュアルな会合が、レストランのバーで開かれた。
チャリティ・ティーパーティのあとで疲れていたのだが、こんなときこそ新しい出会いである。がんばって出かけた。今回は顔なじみの人は少なく、むしろ新しく出会う人たちばかりである。
数名の人たちと言葉を交わしたが、印象的だったのは1975年にWhortonを卒業した老齢のインド人男性。ビジネスを一旦はリタイアして、しかし現在はマイクロファイナンスに関する仕事を立ち上げたとのこと。
アンドラ・プラデシュ州のマイクロファイナンスに対する規制が厳しくなったことを受けて、あれこれと壁が立ちはだかっているとのことだが、娘とともにビジネスを運営しているという。
息子は「インドのAMAZON」として急成長しているFlipkartの創始者だとか。
"www.flipkart.comで本を買ってくれよ!"と、周囲の人たちへしきりに勧めていた。
彼の話で印象的だったのは、1975年当時のWharton。フィラデルフィアの劣悪な治安の話も興味深かったが、それよりも興味深かったのは、当時のアジア人留学生のマジョリティが、日本人だったという事実だ。
夫が在籍中も、日本からの学生を少なからず見かけたが、他の国々に比しては少なく見受けられた。
現在の日本の社会におけるMBAの認知度や重要度が、国際化に伴い高まるというよりも、むしろ低いということもあるのだろうか。
この件に関しては、リーマンショック後の日本のメディアの報道に対しても、書きたいことが山とあった。が、いずれもきちんとした根拠がないことには文字にできないことばかりでそのままとなっている。
フラストレーションがたまる。
このような会合に集まると、欧米とインドは非常に強い絆で結ばれているということを断片的にとはいえ、感じる。一方で、日本が遠い。
それは、どういうことなのか。
たとえばパーティの場において、中国や台湾やシンガポールやコリアンの人たちは、積極的に会話の中に入って行き、交流を深めている人が多いが、日本人は、そのような場に慣れてない人が多い。
それが、何を意味しているのか。
わたしとて、30歳までは日本で暮らし、「こてこての日本文化」の中で育まれて来た。パーティに不慣れだったし、知らない人と話すのも得意ではなかった。しかし、すべては「経験」「慣れ」である。
個人的な次元では、社交性があろうとなかろうと、大した問題ではないだろう。
しかし、こと「国際的なビジネス」となると、話は違う。ましてや海外で暮らし、日本を何らかの形でアピールする立場にある人は、積極的に社交の場へ出ていくべきであろう。その方が、間違いなく、あらゆる意味での収穫が多い。
このような場で、日本人に会うことはほとんどなく、それはいつも残念に思ってきたことの一つだ。
優秀なインドの人々と語り合えば、十把一絡げでインド人を見下し、「日本から来てやっているんだから」といった上から目線の精神構造も改善され、新しい目が開けるであろうに。
ということも、常々感じて来たことである。
……と、話もとびとびに、愚痴っぽいことも含めてまとまりなく書いてしまったが!
この夜は違ったのだ。日本人男性に、出会ったのである。
実はわたしがインドに来て以来、幾度となく仕事をご一緒しているクライアントのバンガロール駐在員の方で、半年ほど前に、こちらへ赴任されたとか。
先日、日本へ帰国し、クライアントを訪問した際、彼の話を耳にしていたのだが、お会いする機会はなかった。偶然、かような場所で遭遇でき、非常にうれしく思った。
基本、夫の付属として参加しているわたしが、何を偉そうに語るかと自覚はしているが、そんなバックグラウンドはさておいてだ。
「日印」の二国間だけでなく、二国間以外の国とのビジネス経験を持っている方が、いろいろな意味で、「強い」と、わたしは思う。
たとえば「日米印」。日本とインドの関係を考えた際、万事につけて日本が優れていると捉える向きが多い。しかしここに米国が入ると、力関係のバランスが変わる。
国家間の結びつき、さらにはビジネスのネットワークの構造が、多分大きく変化する。
というようなことをだらだらと書き連ねても、だからなんなんだと言われるのが落ちかもしれない。それがまた、日本的な反応、ともいえるわけで。
何気なく書くには、テーマがややこしくなってきた。取り敢えず、この辺にしておく。
■GROVERのワイナリーで、テイスティングならぬ飲み放題!
土曜日は、夫婦揃ってOWCのイヴェント(ロードトリップ)に参加。北へ1時間半ほど車を走らせたところにあるGROVER VINYARDSが目的地であった。
詳細は、キレイなブログに記しているので、ご覧いただければと思う。
が、キレイなブログには、きれいごとしか書いていないので、敢えてここで書けば、なんというか想像を遥かに「下回る」、インドだもの。なワイナリーだった。
テイスティングのコーナーも、ピクニックのエリアも、「うちで飲む方がよほどよい」というようなムードであるが、そんな興ざめムードを醸し出したのではつまらんというもの。
新しい出会いあり。
アルヴィンド。ツアーの序盤は、自らのワイナリー巡りの経験及びワインについてのあれこれを同行者に語るなどして、真面目に社交をしていたのだが、テイスティングの中盤から様子が急変。
箸が転げても可笑しい年頃と化し、笑い上戸炸裂。ご機嫌である。
テイスティングなのになぜか皆「酔っぱらっている」という「飲み放題ムード満点な、くだけ感」が漂っていた。
その後は、屋外のコンクリート打ちっぱなしな味気ない一画でピクニックランチ。「え〜、ここなわけ〜? イメージが違う〜〜!」と若干の不平を漏らしつつも、食べる。しゃべる。
と、大いに楽しんだのであった。
が、また行きたいとは、決して思わない。我が家の庭でテイスティングやったほうがずっといい。そんなワイナリーではあった。
こうなったら、マハラシュトラ州のナシック、SULAのワイナリーにはぜひとも足を運び、「お口直し」をしたい! の衝動にかられている。
新聞記事で見つけたアーユルヴェーダの国際見本市。4th World Ayurveda Congress &Arogya Expoと称されたこのイヴェントを訪れた。カルナタカ州政府による組織が主催とあってか、かなり大きな広告も出ていた。
しかし、パレスグラウンドのその会場に足を踏み込むまでは、ここまで大規模なものとは想像していなかった。
期間は5日間。アーユルヴェーダ関連の講演などが行われる一方で、プロダクツを販売する各企業のブースが一堂に会するエキシビションも開催されている。
このエキシビション。多分数百のブースが出ていたはずである。軽く1時間ほどのぞいてみようと立ち寄ったのだが、いつまでたっても出口に到達せず、結局2時間ほども過ごした。
アーユルヴェーダ関連の薬をはじめ、マッサージの器具、ヘルスケアプロダクツなど、無数のブースがひしめきあい、驚くほど多くの来訪者が詰めかけている。
1年前まで暮らしていたムンバイでは、ワールドトレードセンターの向かいに自宅があったこともあり、そこで開催されるさまざまな展示会に足を運んで来た。
そのいずれの展示会の規模をも大きく上回る、このアーユルヴェーダのイヴェント。
詳細は改めて仕事のレポートにまとめるつもりだが、ともあれ、「あまりにもインド的な伝統医療の、その圧倒的なパワー」を肌身に感じた。
一筋縄ではいかない、インド市場の独自性のようなものが、ここには迸っていた。訪問者の顔ぶれ、雰囲気も「独特な感じ」もまた印象的であった。
風貌にせよ、ファッションにせよ、彼らの大半は、西欧化の一途をたどる人々とは異なる。富裕層というよりは、ミドルクラス。ビジネス層というよりは、アカデミック層。
中高年の男女の姿が目立つ。欧米人など外国人の姿は殆ど見られない。超ドメスティックな印象を受けた。この件に就いてもまた、掘り下げて書きたいところだが……。
今日のところは、このへんにしておく。
「キレイなブログ」にここで載せている以外の写真や情報を掲載しているので、ご覧いただければと思う。
★インド発、元気なキレイを目指す日々(第二の坂田ブログ)![]() (←Click)
(←Click)
■インドのワイナリー初訪問@バンガロール郊外
■圧巻! アーユルヴェーダの国際見本市
■家庭的体育会系だった女子の断片。
■今年最後のチャリティ・ティーパーティ